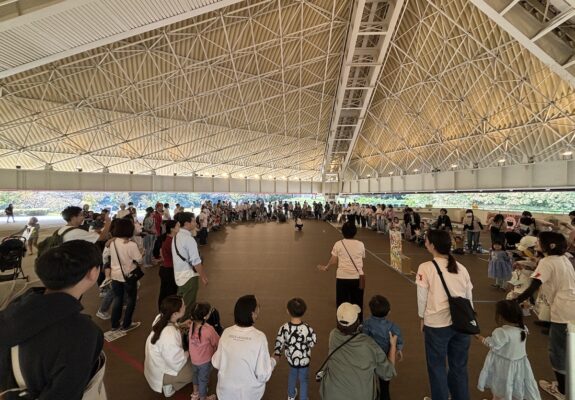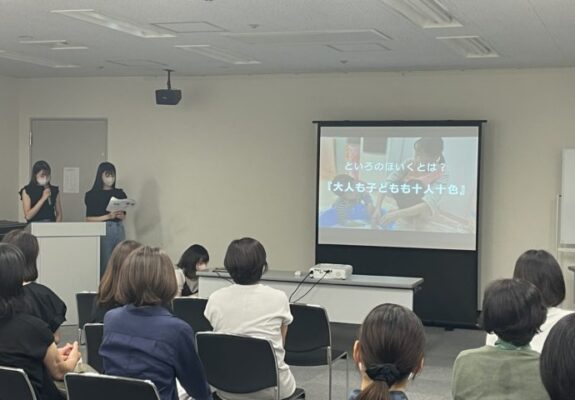CYS school全体研修:非認知能力を育む「やわらかい療育」とは?/事例検討会
#保育型児童発達支援
#代表ブログ
#研修
#CYS school